
白頭大幹の途切れた稜線、標高800mの高地に森の息吹が戻ってきた。1970年代の軍事施設と進入路の開設で深刻に損なわれた「金泉バラムジェ」の物語だ。
昨年9月15日、林業庁は20年間の森林生態回復事業地の中でここを「最優秀事例(対象)」に選定した。これは単なる受賞の知らせではなく、20年の時間がどのように深い傷を癒したのかに関する生々しい記録である。
断絶した土地、傷の記録
1970年代の軍事施設建設と進入路の開設で白頭大幹の稜線が大きく損なわれた。黄岳山の南東の裾野にあるこの地域は「森」ではなく「傷跡」だった。急傾斜の岩盤が露出し、土壌はほとんど流出してしまった。残った土さえも酸性化し、植物が育つのが難しい状態だった。
ここは白頭大幹という巨大な生態軸の腰が切断された「断絶」の現場だった。植物が根を下ろせない死んだ土地だったため、野生動物の移動も妨げられていた。
癒しの第一歩、「基盤」を作る
回復の第一段階は木を植えることではなかった。これ以上傷が悪化しないように「安定」させる作業が優先された。
回復チームは斜面が崩れないように安定化作業を実施した。植物が育つ基盤を作るために外部から健康な土を持ち込み、覆い、酸性土壌を中和する作業を並行して行った。
核心は「自ら回復する力」
本当の回復はその次からだった。この厳しい土地にどんな生命を招待すべきか。回復チームは松やオークの代わりに、厳しい環境でも最初に根を下ろす「先駆種」を選んだ。
白樺、そして特に「オリナム」がその主役だった。
オリナムは自ら土地を肥沃にする力を持っていた。オリナムの根に共生する「根瘤細菌」は空気中の窒素を吸収し、植物が利用できる窒素肥料に変える「窒素固定」能力を持っていた。オリナムは自ら生存することを超え、他の植物が育つことのできない荒れ地を「生きた土地」に変える役割を担った。

20年後、戻った循環
20年が経った今、金泉バラムジェは自ら循環する森になった。1世代目に植えられたオリナムと白樺が立派な森を形成し、その陰で新しい変化が始まった。
鳥たちが運んできた種、特にオーク類のような「極相種」が自然に芽を出し始めた。先駆種が作った基盤の上で森が自ら次の世代を準備する「遷移」過程が起こったのだ。
森が厚くなると動物たちが戻ってきた。イノシシ、カモシカ、ニホンジカの生息痕跡が確認されている。これはバラムジェが単なる「造林地」ではなく、切断されていた白頭大幹の生態軸を再びつなぐ「機能的な森」として回復されたことを証明している。
金泉バラムジェの20年は「速度」ではなく「時間」が、「介入」ではなく「助力」が自然をどのように回復させるかを示している。人間は土地の基盤を作り、最初の癒し手を招待し、残りの分は自然が自らの力で埋めていった。この静かな循環こそが持続可能な回復の核心である。





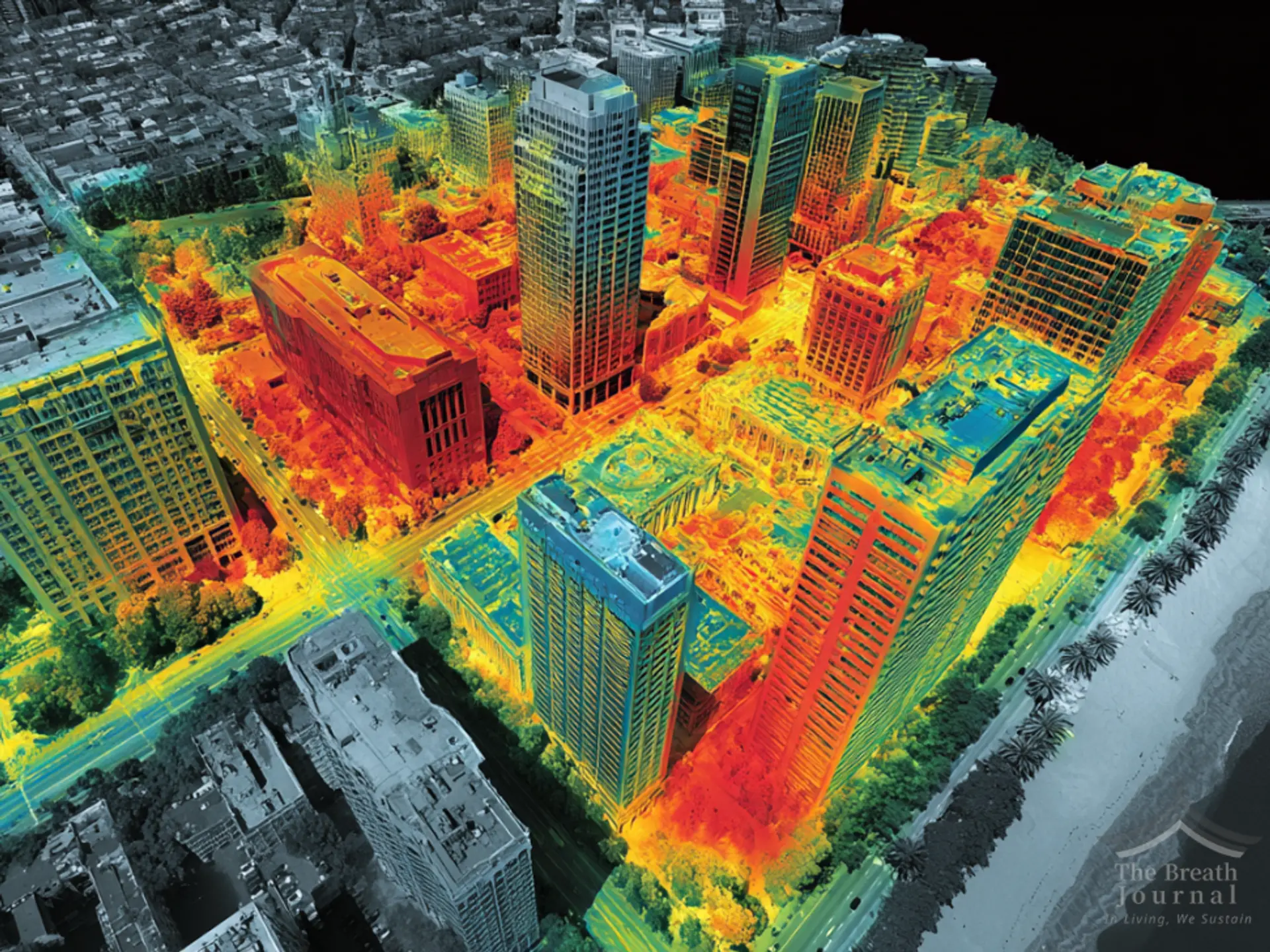




댓글 (0)
댓글 작성