
1926年生まれのイ・ボンジュ職人の生涯には、韓国の近現代史の曲折がそのまま刻まれている。彼は平安北道で習得した伝統技法を守り続けたほぼ唯一の職人であり、彼の人生は1986年に巨大な転機を迎える。鍛えられていた鉄の破片に右目の視力を失う大事故に遭ったのだ。
しかし、彼は絶望の代わりにハンマーを選んだ。手の感覚を守るために大手術を諦め、十日後に再び作業場に戻った逸話は、彼の職人精神を象徴している。このような堅実な自己制御と規則正しい生活が、百寿の年齢にもかかわらず彼の作業を可能にした力だった。
文慶のセント・ジョセフ治癒村に位置するこの建物は、本来銅器職人の伝授館の倉庫兼仮展示場として使われていた空間だった。設計を担当したスタジオ・ヒッチ(代表 パク・ヒチャン、イ・ドンウク)は、ここを彼の人生全体を包み込む叙事的空間、すなわち博物館に生まれ変わらせる道を選んだ。建築の核心は、彼の生涯のように様々な時間を一つの空間に積み上げることだった。
この建築は三つの異なる時間を空間に込めた。既存の建物の赤いレンガの外皮は過去の時間を、内部に積まれた巨大な土圧壁は職人の労働で満たされた生涯を、そして二つの壁の間を歩く観覧者は現在の時間を体験する。このように異なる時間の層が共存し、空間の深みを増している。
また、空間内部は意図的に外部の光と音を遮断し、居心地よく整えられている。これは観覧者が外の世界の妨害なしに、ただ銅器の柔らかな光と空間がもたらす響きに深く集中できるようにするための建築的装置である。これにより訪問者は静かな雰囲気の中で職人の時間と作品に向き合うことができる。
この空間の中心を成す土圧壁は、スタジオ・ヒッチが特に選んだ建築方法である。土圧工法は、土と骨材などを型の中に入れ、層層に固めて堅固な壁を作る伝統技法である。彼らは職人の誠実な生活と何万回ものハンマー打ちで満たされる作業過程を建築的に表現するためにこの技法を採用した。
この土圧工法は、バンジャユギ製作過程の本質とも深く出会う。銅とスズを78対22という厳しい黄金比で合金し、数千回のハンマー打ちに耐えなければ、初めて神秘的な光沢を持つ器が誕生する。土圧工法もまた、土という誠実な材料を数え切れないほどの圧縮の過程を経て初めて一つの堅固な壁となる。
今や職人のハンマーは公式保持者である息子イ・ヒョングン職人と孫イ・ジホ氏に受け継がれ、三代の歴史を作っている。この博物館は銅器を超えた一人の人間の尊厳と継承の価値を語る。結局、この空間が伝える最も深い響きは、一人の誠実な人生が時代を超えて最も大きな遺産となるという事実である。







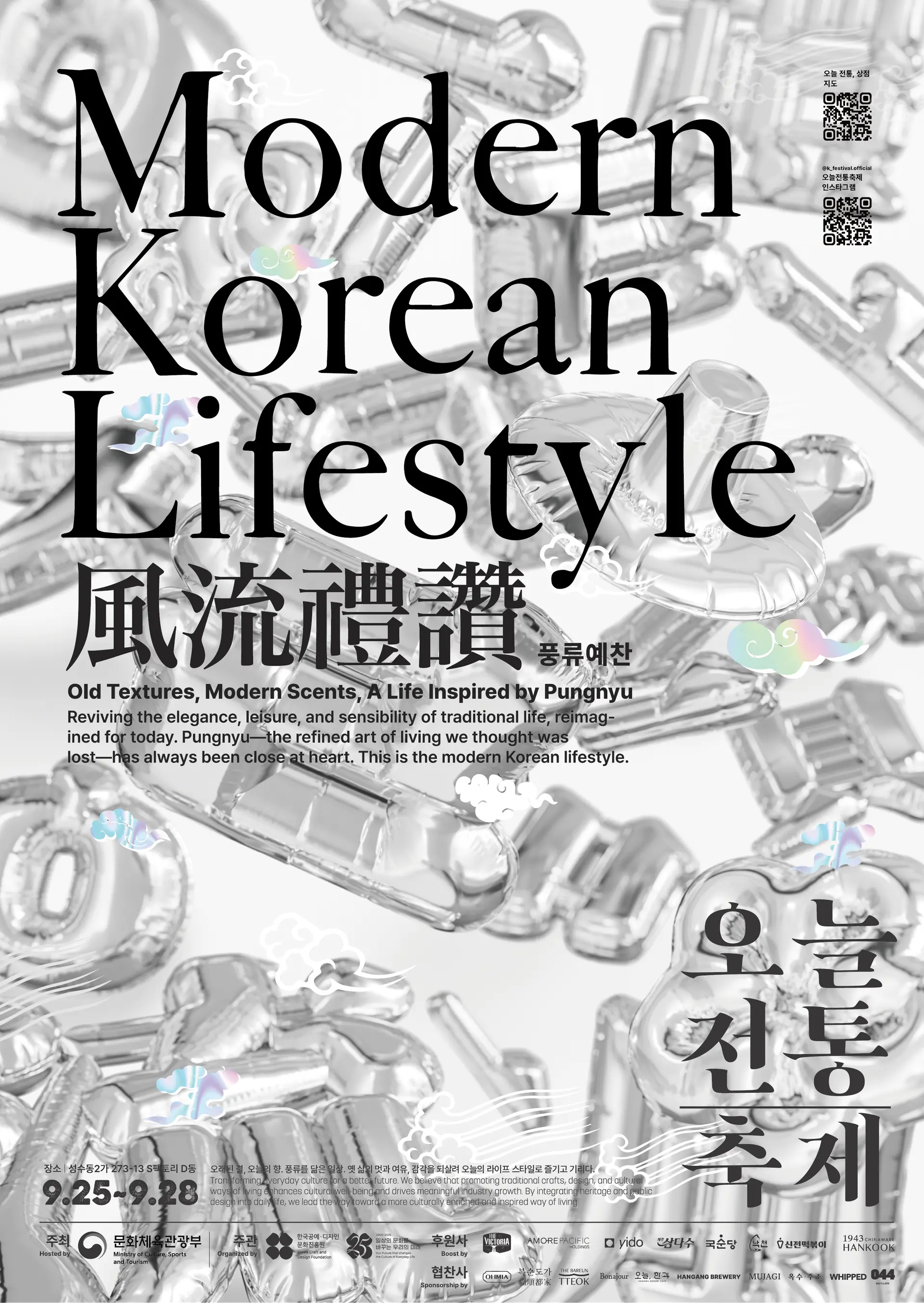


댓글 (0)
댓글 작성