
2025年8月にジュネーブで開催された国連グローバルプラスチック協定(INC-5.2)は、最終文案の採択に至らなかった。この決裂は、状況を変えろという信号と読まれる。条約が停滞していても、都市の調達と企業のバイイングガイドが規範を先行して作り、韓国はバージン絶対削減・再利用基準・毒性透明性で遅いが弱くない合意を準備しなければならない。
ジュネーブで確認したのは文言の隙間ではなく、政治の境界だった。多数の国が生産削減と毒性添加物の規制を明確に要求したが、一部の産油国と生産国は合意を盾にその要求を結局門の外に置いていた。だから今回の決裂は失望でありながら、一つの事実を鮮明に浮き彫りにした。早く合意される協定ほど弱くなる可能性が高いという点だ。
交渉が進展しない間に私たちに必要なのは、焦りの妥協ではない。盤の再設計だ。手続きは、争点ごとの投票や段階的採択のような柔軟性を持たなければならない。交渉の場の外では、すでに機能している規制と基準が同心円を描きながら交渉を引き寄せなければならない。
法の文言より先に動くのは、都市の調達基準と企業のバイイングガイド、そして消費者が実感する運営プロトコルだ。今後1〜2年を見据えると、一つの巨大な条約がすべてを解決するのは難しい。複数の軌道が互いに刺激し合いながら規範を作り出す可能性が高い。野心的連合は法的拘束力が弱くてもガイドラインを先に示し、ヨーロッパを中心とした地域や国の規定は輸出と調達の門を通じて事実上の義務に変わるだろう。
グローバルブランドと流通業者は不確実性のコストに耐えられず、自ら基準を整え始める。バージン樹脂の絶対削減と再利用システムの回転数、そして添加物公開といった定義が購入要件に入ると、交渉の文言が未定でもサプライチェーンはすでに新しい秩序に適応する。条約が停滞しても、規範はこのように進行する。この変化の現場は交渉の場ではなく、都市と市場だ。
では、なぜ都市は常に実験室でなければならないのか。迅速な合意を望む気持ちは正当だが、弱い合意が生み出すロックイン効果はより長い。都市はこのリスクを避けながらも合意を早める通路となる。法律を改正するには時間がかかるが、調達とイベント運営基準は季節が変わる前に変更できる。
祭りの杯が再利用に変わり、公的給食の容器が多回用に転換されると、その日からデータが蓄積される。回収率や洗浄コスト、そして衛生指標や満足度といった数字はすぐに政策設計の言語となる。国際舞台が停滞しているときに必要なのは言葉ではなく証拠だ。大都市の調達基準は即座に市場を説得し、納品業者は包装や添加物、リユース物流を基準に合わせるために設計を変更し、事実上の事前合意を形成する。
何よりも都市は失敗できる空間だ。小さな失敗を許容する場所からのみ、大きな転換の設計図が生まれる。この蓄積があってこそ、速くて弱くない合意が可能になる。現場のデータが交渉の文言を牽引する場面がここから始まる。
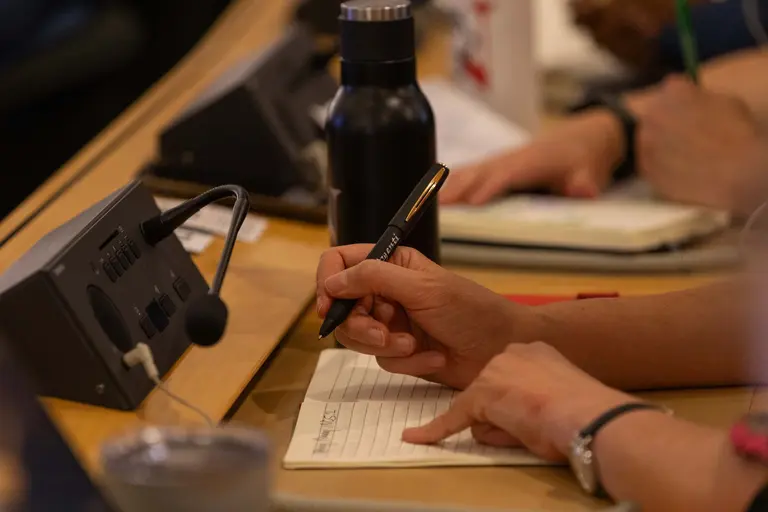
さて、韓国の選択について話そう。必要なのはスローガンではなく、運営と数字の信頼だ。企業の持続可能性報告は、リサイクル率中心の安堵感を脱し、バージン樹脂の絶対削減を前面に置かなければならない。年間総量何パーセントではなく、四半期と製品群単位の細分公示が実際の削減を証明する。
サプライチェーンの一次と二次協力会社と共同目標を設定し、スコープ3を現実にすることももはや先延ばしできない。再利用は原則ではなく基準でなければならない。保証金、洗浄、回収、品質検査、衛生モニタリングを一つのプロトコルにまとめ、国家基準として制定し、地方自治体の調達と大規模イベントを出発点として段階的に適用すれば、投資とスケールアップがついてくる。毒性透明性も急務だ。
どの添加物が入っているのか、どのリスク群をいつまでに排除するのか、どの情報を誰にどう公開するのか、スケジュールを持ったロードマップで提示しなければならない。ヨーロッパと国際ガイド、相互認識可能な枠組みを事前に設計すれば、規定が変わるたびに繰り返される適応コストを大幅に削減できる。このように運営と数字を整えるプロセスが韓国の信頼を生む。そしてその信頼が次の交渉の基盤となる。
政治が停滞した場所で基準が政治を導く。都市の調達基準と企業の購入基準、そして市民が実感する運営プロトコルがまず事実上の合意を作り、その合意が後から国際文言に刻まれる。合意がなければ行動しないという習慣を捨て、生産を実際に減らし、再利用を実際に運営し、毒性を実際に明らかにしよう。こうして蓄積された数字と基準と慣行の厚みが遅い合意を弱い合意にせず、むしろ遅れたが適切な合意を可能にする。









댓글 (0)
댓글 작성